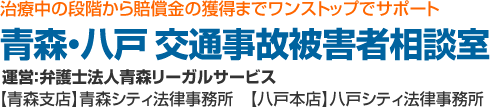2025年11月8日、日本交通法学会関西支部研究会が開催され、弁護士・木村哲也がZoomにより講演を受講しました。
今回のコラムでは、講演の中で解説された大阪高等裁判所令和7年1月20日判決を紹介します。
本判決は、若年未就労の障害者の逸失利益算定方法が問題となったものです。
なお、下記リンク先の関連コラムでは、本判決の原審である大阪地方裁判所令和5年2月27日判決を紹介しています。
【関連コラム】
●日本交通法学会の講演「若年未就労の障害者の逸失利益算定方法について」を受講しました。
本件では、先天性の聴力障害を有していた児童である被害者について、死亡逸失利益の算定が最大の争点となりました。
原審は、聴力障害が労働能力を制限し得る事実であること自体は否定することができないとしたうえで、聴覚障害者平均収入等を参照し、他方、被害者が将来就労するであろう時期には障害者法制の整備を前提とする就労機会等の拡大やテクノロジーの発達によるコミュニケーション手段の充実により聴力障害が就労に及ぼす影響が小さくなると言えるなどとし、全労働者平均賃金の85%を基礎収入とするのが相当であると判断しました。
これに対し、控訴審である本判決は、次のように判示しました。
【判決文の引用】
“未成年者の逸失利益を認定するに当たって全労働者平均賃金を用いる際には、一般に当該未成年者の諸々の能力の高低を個別的に問うことなくその数値を用いているのが通例であり、あえて全労働者平均賃金を増額又は減額して用いることが許容されるのは、損害の公平な分担の理念に照らして、全労働者平均賃金を基礎収入として認めることにつき顕著な妨げとなる事由が存在する場合に限られるというべきである。【被害者】は、先天性の聴覚障害を有していた児童であるところ、【被害者】につき、就労可能年齢に達した時点における基礎収入を当然に減額するべき程度の労働能力の制限の有無やその程度を検討するに当たっては、死亡当時の【被害者】固有の聴覚の状態像を正確に理解した上で、就労可能年齢に達したときの【被害者】の労働能力の見通し、聴覚障害者をめぐる社会情勢・社会意識や職場環境の変化を踏まえた【被害者】の就労の見通しを検討して、【被害者】の労働能力を評価すべきであると考えられる。”
そのうえで、本判決は、「【被害者】の中枢系能力は、平均的なレベルの健聴者の能力と遜色ない程度に備わり、聴力に関しても、性能が飛躍的に進歩した補聴器装用に併せて、一定程度不足する聴力の不足部分を手話や文字等の聴力の補助的手段で適切に補うことにより、支障なくコミュニケーションができたと見込まれるから、【被害者】は、聴覚に関して、基礎収入を当然に減額するべき程度に労働能力の制限があるとはいえない状態にあるものと評価することができる」と認定し、「障害者法制の整備、テクノロジーの目覚ましい進歩、さらには聴覚障害者に対する教育、就労環境等の変化等、聴覚障害者をめぐる社会情勢や社会意識が著しく前進していく状況」、「障害の「社会モデル」の考え方が浸透し、事業主の法的義務となった社会的障壁を除去するためのささやかな合理的配慮の提供として、聴覚障害者に対し様々な補助的手段の併用が認められ、聴覚障害者がそれらを駆使して、健聴者とともに同じ条件で働く職場環境が少なからず構築されているといった、聴覚障害者をめぐる就労現場の実態」などを踏まえ、全労働者平均賃金を基礎収入として認めることにつき顕著な妨げとなる事由はないと判断しました。
※「聴覚」とは、末梢系(音の情報を伝達する生理学的な機能。「聴力」に関わる)と中枢系(伝達された音の情報を分析し、言語あるいは音楽として理解する心理学的な機能)の2つを合わせたシステムです。
※「障害」の捉え方として、障害は病気や外傷等から生じる個人の問題であり、医療を必要とするものであるという旧来の「医療モデル」の考え方と、障害は主に社会によって作られた障害者の社会への統合の問題であるという現在の「社会モデル」の考え方があり、「社会モデル」の考え方を踏まえて障害者法制の整備等が行われています。
結論として、本判決では、全労働者平均賃金を基礎収入とする死亡逸失利益の算定が認められました。
そして、その後、本判決は確定しています。
このように、若年未就労の障害者の逸失利益算定においては、本判決の判示を引用すれば、「全労働者平均賃金を基礎収入として認めることにつき顕著な妨げとなる事由」の有無が争われることとなります。
そして、被害者側としては、被害者固有の障害の内容・程度、就労可能年齢に達したときの被害者の労働能力の見通し、障害者をめぐる社会情勢・社会意識や職場環境の変化を踏まえた被害者の就労の見通しを、丁寧に主張・立証していくことが求められると考えられます。
(弁護士・木村哲也)